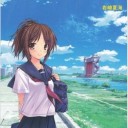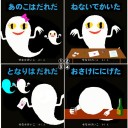突入である
早いのである
「あん あん あん とっても大好きどらえもん・・・」
どらえもんは、誰と何をしていたんでしょうか?
http://blog.livedoor.jp/kinisoku/archives/4677982.html
考え付かんかったな
早いのである
「あん あん あん とっても大好きどらえもん・・・」
どらえもんは、誰と何をしていたんでしょうか?
http://blog.livedoor.jp/kinisoku/archives/4677982.html
考え付かんかったな
自己啓発系のスローガンにもできそうなのである
あなたが知的であるかどうかは「五つの態度」でわかる。
一つ目は、異なる意見に対する態度
知的な人は異なる意見を尊重するが、
そうでない人は異なる意見を「自分への攻撃」とみなす。
二つ目は、自分の知らないことに対する態度
知的な人は、わからないことがあることを喜び、怖れない。
また、それについて学ぼうする。
そうでない人はわからないことがあることを恥だと思う。
その結果、それを隠し学ばない。
三つ目は、人に物を教えるときの態度
知的な人は教えるためには自分に「教える力」がなくてはいけない、と思っている。
そうでない人は教えるためには相手に「理解する力」がなくてはいけないと思っている。
四つ目は、知識に関する態度
知的な人は、損得抜きに知識を尊重する。
そうでない人は、「何のために知識を得るのか」が
はっきりしなければ知識を得ようとしない上、役に立たない知識を蔑視する。
五つ目は、人を批判するときの態度
知的な人は、「相手の持っている知恵を高めるための批判」をする。
そうでない人は、「相手の持っている知恵を貶めるための批判」をする。
http://www.mudainodocument.com/articles/37982.html
あなたが知的であるかどうかは「五つの態度」でわかる。
一つ目は、異なる意見に対する態度
知的な人は異なる意見を尊重するが、
そうでない人は異なる意見を「自分への攻撃」とみなす。
二つ目は、自分の知らないことに対する態度
知的な人は、わからないことがあることを喜び、怖れない。
また、それについて学ぼうする。
そうでない人はわからないことがあることを恥だと思う。
その結果、それを隠し学ばない。
三つ目は、人に物を教えるときの態度
知的な人は教えるためには自分に「教える力」がなくてはいけない、と思っている。
そうでない人は教えるためには相手に「理解する力」がなくてはいけないと思っている。
四つ目は、知識に関する態度
知的な人は、損得抜きに知識を尊重する。
そうでない人は、「何のために知識を得るのか」が
はっきりしなければ知識を得ようとしない上、役に立たない知識を蔑視する。
五つ目は、人を批判するときの態度
知的な人は、「相手の持っている知恵を高めるための批判」をする。
そうでない人は、「相手の持っている知恵を貶めるための批判」をする。
http://www.mudainodocument.com/articles/37982.html
書いておいた方が良いのではないかというね
これはまさしく「mement mori」の世界であって
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%AA
これはまさしく「mement mori」の世界であって
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%AA
久しぶりに数学に取り組んでいる訳だが
なんだか凄いものだったのだなと思ってね
結局学校で教える数学というものが何かというと
数学的真理を用いて課題を解決するということであってね
数学の世界には余弦定理とか中点連結定理とか
絶対的な正しさがある訳よ
それを与えられた問題にどう活用して解を見つけるかという
なかなか面白い構造なのだなと
数学者になるでもなければ数学そのものは役に立たんと
まあそれはそうかもしれんわね
ただし社会に出た時に役に立つというのはつまりこの思考法であって
つまり会社から「今回の商談は1マソまで値引きしていい」という「正しさ」を与えられたとき
それをどう活用して客との商談に取り組むのかという
これが数学的思考の活用になるのではないかなと
数学なら補助線を引いたり既に習った別の定理を使ってみたり
いろいろ工夫して解を求めようとするわね
4510においても室温を工夫してみたり茶でも出してみたり
今までの交渉で使った定理やその時の解なんかも確認しながら
そんでここぞという時に「1マソ値引きの定理」を繰り出して
見事商談を成功させるというか
これを論理的思考に基づいて行っているのであれば
実に数学的であると思った
そうすると数学の魅力は絶対的な正しさが存在するということかな
定理は誰がやっても何度やっても同じ結果になるので定理だわね
そうすると課題はそれを使うタイミングを見極めること
それを使えるような環境を整えることになる訳である
商談はそうはいかんわね
人によっても結果が変わるし状況によっても結果が変わる
そもそも誰にでも通用する定理はないし
解も一つではないことがある訳である
金が素晴らしいツールていったって
幾ら積んでもそれに転ばない人間もいるし
命が素晴らしいツールていったって
使命の為にそれを投げ出す人間もいるし
ファ○クが素晴らしいツールていったって
そこに興味を持たない人間もいるし
まあ最後の例はいらんかったかもしれないが
だから絶対的正しさを持った問題解決の為のツールがあって
それを正しく使えればひとつの解を求められる構造というのは
実に美しいなと思った訳である
数学に魅かれる人がいるというのをようやく少し理解できた気になったのである
まあ高校時代IAあたりで嫌になって
数学の時間はお昼寝時間になっていた人間からすると
経験によって新たな視点が加わったなということと
この視点は気付きを与えて揺さぶる時の一つのツールになるかもしれないと
その位の認識ではあるのだが
なんだか凄いものだったのだなと思ってね
結局学校で教える数学というものが何かというと
数学的真理を用いて課題を解決するということであってね
数学の世界には余弦定理とか中点連結定理とか
絶対的な正しさがある訳よ
それを与えられた問題にどう活用して解を見つけるかという
なかなか面白い構造なのだなと
数学者になるでもなければ数学そのものは役に立たんと
まあそれはそうかもしれんわね
ただし社会に出た時に役に立つというのはつまりこの思考法であって
つまり会社から「今回の商談は1マソまで値引きしていい」という「正しさ」を与えられたとき
それをどう活用して客との商談に取り組むのかという
これが数学的思考の活用になるのではないかなと
数学なら補助線を引いたり既に習った別の定理を使ってみたり
いろいろ工夫して解を求めようとするわね
4510においても室温を工夫してみたり茶でも出してみたり
今までの交渉で使った定理やその時の解なんかも確認しながら
そんでここぞという時に「1マソ値引きの定理」を繰り出して
見事商談を成功させるというか
これを論理的思考に基づいて行っているのであれば
実に数学的であると思った
そうすると数学の魅力は絶対的な正しさが存在するということかな
定理は誰がやっても何度やっても同じ結果になるので定理だわね
そうすると課題はそれを使うタイミングを見極めること
それを使えるような環境を整えることになる訳である
商談はそうはいかんわね
人によっても結果が変わるし状況によっても結果が変わる
そもそも誰にでも通用する定理はないし
解も一つではないことがある訳である
金が素晴らしいツールていったって
幾ら積んでもそれに転ばない人間もいるし
命が素晴らしいツールていったって
使命の為にそれを投げ出す人間もいるし
ファ○クが素晴らしいツールていったって
そこに興味を持たない人間もいるし
まあ最後の例はいらんかったかもしれないが
だから絶対的正しさを持った問題解決の為のツールがあって
それを正しく使えればひとつの解を求められる構造というのは
実に美しいなと思った訳である
数学に魅かれる人がいるというのをようやく少し理解できた気になったのである
まあ高校時代IAあたりで嫌になって
数学の時間はお昼寝時間になっていた人間からすると
経験によって新たな視点が加わったなということと
この視点は気付きを与えて揺さぶる時の一つのツールになるかもしれないと
その位の認識ではあるのだが
それでもまあお誘いいただいたのだからと
2016年6月11日 宗教・自己啓発朝起きてきたのである
理論と実践という観点で輪読があったのだが
テキストの趣旨でいえば
どちらかといえば実践が重要であるとこういうことであった
勿論そこに一定の理解は示す訳で
つまり理論先行型で行動が伴わないとすると
これは只のコメンテーターであるからそこにそれ程価値はないというかね
こちらの思考に引き付けて言えばこれは「リングに上がれ」ということである
しかしながらよ
自身が組み立てたロジックに当てはめると
あんまり捉えていない気になってしまうね
という訳で考えようと思ったのだが
相当複雑構造なので纏めるのに時間がかかりそうだな
理論と実践という観点で輪読があったのだが
テキストの趣旨でいえば
どちらかといえば実践が重要であるとこういうことであった
勿論そこに一定の理解は示す訳で
つまり理論先行型で行動が伴わないとすると
これは只のコメンテーターであるからそこにそれ程価値はないというかね
こちらの思考に引き付けて言えばこれは「リングに上がれ」ということである
しかしながらよ
自身が組み立てたロジックに当てはめると
あんまり捉えていない気になってしまうね
という訳で考えようと思ったのだが
相当複雑構造なので纏めるのに時間がかかりそうだな
という話かとも思ったのだが
人間の発達における要素として
それは遺伝によって決まるというゲゼルが唱えた成熟優位説
それは環境だよというワトソンが唱えた環境優位説
いやいやどちらの要素もあるよという中に
輻輳説のシュテルンや環境閾値説のジェンセンなどがいる訳だね
さて遺伝というのはDNAレベルの話であるが
前回からの話を
http://17997.diarynote.jp/201603251946139506/
更に深める記事があったもので
それを使って考えてみようではないかと
つまりDNAは体の設計図で
体というのは入れ物だわね
そこに入るものが魂であるとすると
魂の質によって個性が影響を受ける可能性があるのではないか説
ということである
以下抜粋
http://chaos2ch.com/archives/4607292.html
人は何度も生まれ変わりを繰り返す。
ほとんどの人は前世があり、そのまた前世がある。
前世の回数に比例して魂レベルが高くなる傾向がある。
つまり、前世の回数が多いほと大人の魂といえる。
ではいったい自分の魂の年齢はどの程度なのか?
前世を知り得ない以上、推測するのは困難である。
だから、魂年齢に応じた特徴などを述べる。
魂の年代には大きくわけて5段階ある。
乳児期。「今、ここ」を生きる。模倣する。
幼児期。文明構造をつくる。
若年期。権力問題。名声、金銭に関心がある。
成人期。感情的な学び。人間関係。自己、カルマとの取り組み。
老年期。日常的な感情問題を超越。知的な表現。人に教える才能がある。
超越期。高次のレベルとの結びつき。
無限期。すべてに気づく。
簡単に言うと、
人間として初めて生まれてくると、アフリカの原住民族のような所に生まれてくる。(乳児期)
そこで数回の転生ののちに、発展途上国に生まれてくる。(幼児期)
独裁者が支配する国の元で
独裁者の決めた規則に従って生きることが快適であり正しいと考える。(幼児期前半)
独裁政権に息苦しさを感じ、
来世で民主主義の国に生まれ自分の力を試したくなる。(幼児期後半)
民主主義の国で成功や名誉を求め、がむしゃらに頑張る。
ある程度の地位や富を得て満足している。(若年期前半 )
しだいに富や地位のために人と争うことに疲れてくる。
そして宗教とか平和というものを意識しはじめる(若年期後半)
精神性に目覚め宗教心に目覚めて、心を大切に生きようとする。(成人期前半)
しかし心を意識して生きるようになると、他人の悪感情が突き刺さり、
物質社会や争いで次第に精神を病む。(成人期中半)
病を克服し心霊力が備わり、神の存在を求め出す(成人期後半)
自分や他人は神の子であると知ることによって、
一切衆生に対する慈悲心がでてくる。(老年期前半)
宇宙の真理を悟る。守護霊や神仏とチャネリングしたりして生きる。
自己流の霊的な道を突き進む(老年期後半)
人間の発達における要素として
それは遺伝によって決まるというゲゼルが唱えた成熟優位説
それは環境だよというワトソンが唱えた環境優位説
いやいやどちらの要素もあるよという中に
輻輳説のシュテルンや環境閾値説のジェンセンなどがいる訳だね
さて遺伝というのはDNAレベルの話であるが
前回からの話を
http://17997.diarynote.jp/201603251946139506/
更に深める記事があったもので
それを使って考えてみようではないかと
つまりDNAは体の設計図で
体というのは入れ物だわね
そこに入るものが魂であるとすると
魂の質によって個性が影響を受ける可能性があるのではないか説
ということである
以下抜粋
http://chaos2ch.com/archives/4607292.html
人は何度も生まれ変わりを繰り返す。
ほとんどの人は前世があり、そのまた前世がある。
前世の回数に比例して魂レベルが高くなる傾向がある。
つまり、前世の回数が多いほと大人の魂といえる。
ではいったい自分の魂の年齢はどの程度なのか?
前世を知り得ない以上、推測するのは困難である。
だから、魂年齢に応じた特徴などを述べる。
魂の年代には大きくわけて5段階ある。
乳児期。「今、ここ」を生きる。模倣する。
幼児期。文明構造をつくる。
若年期。権力問題。名声、金銭に関心がある。
成人期。感情的な学び。人間関係。自己、カルマとの取り組み。
老年期。日常的な感情問題を超越。知的な表現。人に教える才能がある。
超越期。高次のレベルとの結びつき。
無限期。すべてに気づく。
簡単に言うと、
人間として初めて生まれてくると、アフリカの原住民族のような所に生まれてくる。(乳児期)
そこで数回の転生ののちに、発展途上国に生まれてくる。(幼児期)
独裁者が支配する国の元で
独裁者の決めた規則に従って生きることが快適であり正しいと考える。(幼児期前半)
独裁政権に息苦しさを感じ、
来世で民主主義の国に生まれ自分の力を試したくなる。(幼児期後半)
民主主義の国で成功や名誉を求め、がむしゃらに頑張る。
ある程度の地位や富を得て満足している。(若年期前半 )
しだいに富や地位のために人と争うことに疲れてくる。
そして宗教とか平和というものを意識しはじめる(若年期後半)
精神性に目覚め宗教心に目覚めて、心を大切に生きようとする。(成人期前半)
しかし心を意識して生きるようになると、他人の悪感情が突き刺さり、
物質社会や争いで次第に精神を病む。(成人期中半)
病を克服し心霊力が備わり、神の存在を求め出す(成人期後半)
自分や他人は神の子であると知ることによって、
一切衆生に対する慈悲心がでてくる。(老年期前半)
宇宙の真理を悟る。守護霊や神仏とチャネリングしたりして生きる。
自己流の霊的な道を突き進む(老年期後半)